フォーラムでは、数多くの医療アプリ、システムの実例が国内外問わず多数報告された。自らが開発者でもある宮川一郎氏(習志野台整形外科内科院長)、三宅琢氏(眼科医、神戸理科科学研究所客員研究員)の講演を中心に、国内事例の報告を紹介する。
医療健康情報共有によるQOL マネージメント・コンセプト/宮川氏
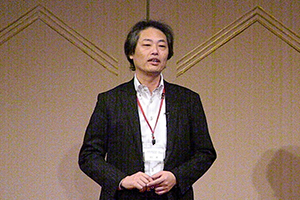
習志野台整形外科内科院長/
メディカクラウド株式会社 顧問 宮川一郎氏
宮川氏(医療法人社団NICO習志野台整形外科内科 院長、メディカクラウド株式会社 顧問)のセッションでは、まず50年後の人口推計グラフに「65歳以上の高齢化率」と「現役医師数の独自予測数」「OECD平均医師数」を反映させたスライドから始まった。医師として、今後の医療体制、医療充実を考えるなかで現在重要視しているのが「QOL マネージメント・コンセプト」だという。
事業活動理論の1つである「PDCA」の視点で医療を見たとき、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(監視)」「Action(改善)」のサイクルを回すためにマネージメントは必須であり、もっと健康情報を活用するさまざまなツールが存在しても良いのではないかと開発を行ってきた。
宮川氏は自ら開発を手がけた事例のうち、大きく3つのツールをあげた。
1つめは医療現場でのツールで、患者コミュニーケションの時間作り出す目的で開発した「iPad問診票」やコミュニーケションの質を上げる目的のCGアニメーションによる患者説明ツール「IC動画HD」、患者が持つ健康情報を取得する目的として開発したハイブリット型再診受付機である。
2つめは個人別の識別 ID を記したQRコード(2次元バーコード)のシールをお薬手帳や血圧手帳に貼ったり、活動量計を診察券にしてしまう、いわば「手帳(健康情報)の診察券化」の取り組み。これなら必ず手帳を持って来てもらえる。それまで患者の普段の様子は、紙の活動ノートに記入・持参してもらうことでチェックしていたがなかなか継続が難しく、それ自体を忘れてくる患者も多い。患者が持つデータを提供されるまで待つのではなく、 弱い“強制力”を加え提供してもらうよう導くわけだ。患者にとっての利便性が良くなっただけでなく、「Check(監視)」「Action(改善)」体制がうまく機能することで、何より健康に対する気づきも多く意識が上がったという。
3つめは、よりヘルスケアに寄った仕組みで2014年にリリースした「健康サイネージ」。柏の葉キャンパス駅の商業施設内に設置されたサイネージ機に活動量計をかざすと活動量や消費カロリーなどの情報を表示し、活動量に応じた「ポイント」が付くサービス。
2015年からは自社の従業員向けに活動量と勤怠管理(タイムカード)と連動させて社員が共有できる「健康タイムカード」を発表した。これはふだん空気のように考えられ価値を感じづらい、自身の健康に対する動機付けとしてポジティブインセンティブやネガティブな強制力を持つサービスと連動させることにより結果的に行動変容に繋がり、PDCAを回していくための環境づくりができるとの見方を示した。
医療と健康の情報が統合される時代へ
今後は医療情報と患者の健康情報が一体化され、医療は、断面を見るのではなく全体を俯瞰するようになっていくだろう、と宮川氏。これらの情報をいかにアップデートし続けてもらい、そしていかに取得し続けていくかが、これからの国民の健康維持にとって重要になるとした。例えば、人々の健診や過去の受信歴を一元管理できれば、そのデータをもとに調査や新薬の開発へつなげることができる。諸問題はあるものの、こうした方向に向かっていくであろうとした。
そのためには、単にIT技術やビックデーターだけでなく、みんなでアイデアを出し続け世の中を変えて行こうと締めくくった。
視力ではなく「意欲」の向上を図る「デジタルビジョンケア」/三宅氏

Studio Gift Hands 代表取締役/
神戸理化学研究所 客員研究員 三宅琢氏
続いて登壇したのは、薬の処方をせず、手術もしない眼科医だという三宅琢氏(Studio Gift Hands 代表取締役、神戸理化学研究所 客員研究員)。彼の患者は、主に全盲や弱視、読み書きのできない学習障害を持つ子どもたちだ。そうした彼らにはそもそも視力を向上させるという、いわゆる「治療」が極めて困難だ。ゴールがそこではないことに気がついたという三宅氏は、彼らに対してタブレットやアプリなどのアイデアを紹介する「デジタルビジョンケア」を行っている。視力ではなく意欲を向上させるために、「気づきの処方箋」を出しているのだという。
例えば、電子書籍。文字が拡大できるから本が読めると思われがちだが実際は、文字を拡大すると文章が画面からあふれてしまうため、画面を何度も上下にスクロールしなければならない。これは読む意欲を阻害してしまうことにつながる。文字サイズや背景色、フォントや文章の縦横の構造を変えることができれば、人は「本が読みたい」という意欲が湧くというのだ。産業医になって最初に開発したスタンドは、文字の拡大と白黒反転ができるもので、安くて機能性のあるものだった。これを使用した最初の患者は、本を読むのではなく食事に活かした。ご飯の上にスタンドを置き、拡大してしっかり見てから食べると「何十年ぶりかに味の記憶がした」という。また、別の全盲の患者は、かざすだけでお金を読みあげてくれるマネーリーダーというアプリを使い、世界一周旅行を何不自由なく楽しんでいるとのこと。
患者の不便さに気づき、それを解消できるツールを開発・紹介することが「治療」とも言えるのである。
人が障害に合わせる時代は終わり
視覚障害とは、視力によって必要な情報が得られないアクセス障害である。それに気がついた三宅氏は、障害を克服することではなく、障害によって不便を感じる環境をなくすことが重要であると考えた。ICTは、自分の不便な環境をなくすことができるツールになる。虫眼鏡などを使って文字を拡大させるような「人が障害に合わせる時代」は終わり、「情報が障害に合わせることができる時代」になっている。医療は患者の未来を作り得るが、デジタルデバイスによるロービジョンケアは、患者が困っているその瞬間の「今」を未来につないでくれる処方箋となり得るのだ、と結んだ。
神戸医療イノベーションフォーラム2015レポート
- 臨床と研究の最前線から生まれたプラクティスとは
- 医療ICTの最新事例報告(前編・国内編)
- 医療ICTの最新事例報告(後編・海外編)
- イノベーションを起こす核は何か、そして本当に求められるイノベーションとは








