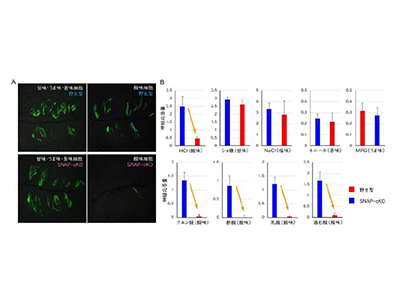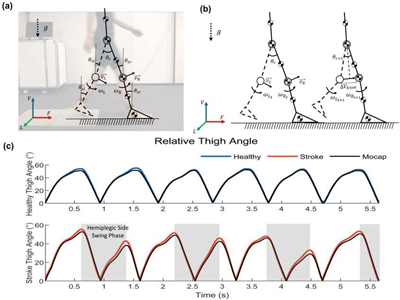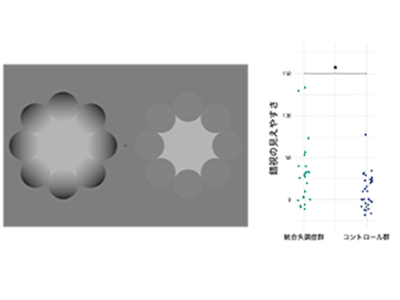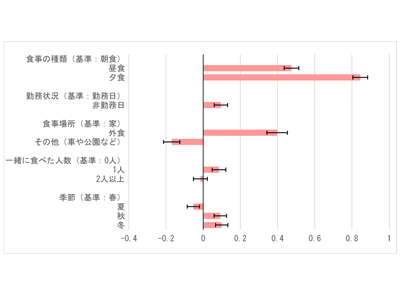“患者さんにやさしい治療”に加えて個別化へ
本日はPULMOMICS誌のテーマである個別化医療について、外科医の視点からお話しをしたいと思います。
世界的に見ても、肺がんの外科治療は個別化が加速していると言えるでしょう。私が医師になった30年前は「肺がんの手術で創の大きさは気にするな」と先輩から教えられました。がんを確実に取るのが最重要なので、創の縮小など本末転倒だということです。しかし、時代は変わりました。今は創を小さくすること、さらに肺活量をできるだけ残すことを、がんを確実に取るのと同じくらいの価値で考えます。そうした総合的な判断が、患者さん一人ひとりにあわせたバリエーションを外科治療にもたらしているのです。
患者さんにやさしい低侵襲手術の方向性としては、アプローチの選択と縮小手術がトピックになっています。アプローチには大きく分けて開胸手術と胸腔鏡手術があります。患者さんにとって創や痛みは大きな問題です。そこでこの20年ほどで発達してきたのが、創が小さく、肋骨や筋肉を切らずにすむ胸腔鏡手術でした。胸腔鏡手術にも完全モニター視下で行うVATS1と、私の得意とするハイブリッドVATS2の2つのパターンがあります。さらに、一般的な胸腔鏡手術では4〜5カ所程度、ハイブリッドVATSでは2カ所のポート孔が必要なところを、1カ所で済ませようというユニポートVATSも流行ってきています3。
縮小手術には区域切除と部分切除があり、いずれも現在の標準治療である肺葉切除と比べ肺をなるべく小さく切ることで、肺活量の温存を目指す考え方です。2021年の米国胸部外科学会4においてJCOG0802試験の結果が発表され、教科書が変わるような内容だと話題になりました。この試験は2cm以下の肺野末梢小型非小細胞肺がんに関して、肺葉切除と区域切除の全生存期間(OS)を比較した大規模な第Ⅲ相試験です。
2018年にはロボット手術も保険適用になり、アプローチの選択はさらに複雑化してきています。術者の経験とレベル、ポリシーによるところが大きく、仮に日本の治療成績トップ10の医療機関を肺がんで受診したとしたら、おそらく治療方針はそれぞれで異なるでしょう。
縮小手術を支えるハイブリッド
縮小手術が重要視されるなかで、胸腔鏡手術を完全モニター視下とハイブリッドのどちらで行うか。創の大小ではどちらが低侵襲と言いがたく、術者それぞれの「どちらがやりやすいか」という考え方によってきます。私自身はハイブリッドしか行わない理由をお話ししましょう。
ハイブリッドVATSは、カメラを入れる1cmの創の他に4〜5 cmの創を置きます。切除した肺を取り出すのに必要だからというのと、4cmより狭いと両眼で立体視できないからです。両眼で見ることができなければ、奥行きがわかりません。基本的にモニター視では2Dですから、奥行きがわからないのです。
肺葉切除では、もともと肺葉は分かれているので、血管と気管支を切れば多くはきれいに取ることができます。一方で区域切除では、区域というものは分かれていないので、肺の実質を切っていかないといけません。それが難しい。腫瘍からマージンを必要十分確保して肺実質を切離しなければなりません。奥行きがわからないのは、術者にとっては手を縛られて手術するのと同じくらいのハンディだということです。患者さんが命を預けてくださっているのに、不安を感じながら手術をする自分を許すことはできません。だから私には、ハイブリッドが必要なのです。
ちなみに、完全モニター視下であってもロボット手術はたくさん行っています。3Dだからです。ただ、ロボット手術は「木を見て森を見ず」に陥りがちです。拡大視できるメリットは大きいのですが、全体を遠目から把握することが難しい場合があるロボットで区域切除を完璧に実施するのは今後の課題です。
外科医として“超一流”であるための薬の知識
肺がんの外科治療をさらに個別化し、複雑にしている要因は、集学的治療の発達です。手術の前後に患者さんの状態や病変の進行度・病理結果を見ながら、薬物治療や放射線治療を行うのか?薬物治療はどの薬をどれだけ使うか?考えなければいけません。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬など新薬がたくさん登場し、薬物治療は複雑になっていると思いますが、最新の外科手術治療も同じなのです。
例えばEGFRに変異がある患者さんであれば、分子標的薬が効くと予想されます。高齢で拡大手術に耐えられそうにないと判断すれば、できる限り分子標的薬で治療し、残存時や再発時の小さな腫瘍は手術で取る「サルベージ手術」という選択肢が出てきます。若くて元気であればまず手術(術前薬物治療を考慮)、再発したときに分子標的薬を使おう、という選択肢もあるでしょう。どちらの選択がより有効か・低侵襲かというのは、術者によって考え方が違います。また免疫チェックポイント阻害薬を術後の補助治療(アジュバント療法)に用いる研究治験も多数進められており、術前(ネオアジュバント療法)にも広がってきています。薬物治療での有効性と外科治療における有効性とは別問題ですが、概して外科の患者さんはすでに転移・再発をした薬物治療のみ適用となるような患者さんよりも元気なので、薬の効き目が出やすい傾向にあるようです。
外科医は手術前の画像診断から、手術の現場、手術後の病理、補助治療まで、すべてフォローし、学ぶことのできるポジションにあると言えます。一方、内科に来た患者さんは内科が薬で治療する、外科に来た患者さんは外科が手術で治療する、と縦割りの専門病院も多いと聞きます。それでは、患者さんにとって何がベストか、総合的な判断はできないですよね。
私の前所属である兵庫県立がんセンターでは、週1回キャンサーボードといって、内科、外科、放射線科、病理診断科の集まるカンファレンスを行っていました。そのときは本当に戦々恐々でしたよ。内科トップの里内美弥子先生と外科トップの私とで、「その患者さんは手術の適応から外れるのではないか」「いや、あの薬をここまで入れた後、手術で取りきろう」「いや、まず手術をして、病理を見てから薬を決めよう」と、傍から見えれば“症例の取り合い”のような真剣な議論が繰り広げられていたからです。
内科の先生が手術のことも勉強する。外科の先生も薬のことも勉強する。この切磋琢磨が絶対必要だと思います。私の教室は、研究・臨床を問わず、全国の外科のなかで薬を使う頻度が非常に高いと思います。自分の得意な所で一流を目指すのは当然です。われわれはすべての方面で“超一流”を目指し、日夜、最新の薬にも精通するよう勉強しています。
求められる、より難しい判断
肺がんは高齢者に多いので、従来は「手術できるかどうか(適応かどうか)」の判断が主でした。それが今は「すぐに手術ではなく、集学的治療であればどうか」という判断が必要になりました。ステージ3や4で脳転移があっても、薬物治療や放射線治療を徹底的に行い、残ったところだけ取る、または新病変が出現したら取るというサルベージ手術が増えました。そのような手術は薬や放射線の影響で組織が脆く癒着が激しくなっているため難しく、外科医はますます腕を上げないといけません。
近い将来、日本からエビデンス発信した区域切除が世界的にメジャーになっていくがゆえに、新しい議論が生まれる可能性もあります。例えば高齢者や併存症をもつ患者さんには「肺活量を残すためにがんの根治性が多少落ちる恐れがある縮小手術を選択してよいか」。患者さんにとって、肺活量温存のメリットはそれほど大きいのです。がんは取れたとしても、寝ているだけで苦しく酸素吸入が必要、というのでは辛いですから。
さらには「手術をしない」判断も求められるようになってきています。日本が得意とするCTやPETなどの診断技術の発達によって、2cm以下の小型腫瘤が爆発的に多く見つかるようになっています。そうなると、早く小さく見つかったものをいかに低侵襲に取るか、あるいは取らないでフォローするか悩む機会が増えるわけです。当然、がんと細胞学的に診断されたら取ることを考えますが、早期の腺がんは何年かあまり大きくならない場合もたくさんあります。手術のリスクはゼロではないので、切らないに越したことはないのです。
患者さんの期待に応える医師であれ
普段から若い先生方に、自分に命を預けてくれる患者さんに感謝し、一例一例を大事にするように指導しています。症例の多い病院でたくさんの患者さんを相手に業務をこなすというのも、レベルアップの1つの手段でしょう。でもやはり、一人ひとりの患者さんを最初から最後まで責任もってきちっと診て、反省点を次に生かしていくことが必要です。
もう1つ、「自分が患者さんだったらどうしてほしいか」という気持ちを大切にしてほしい。例えば進行がんで、薬物治療と放射線治療を限界まで行い、あとは手術でなんとかなりませんか? という相談があったとしましょう。危険の多い、難しい手術です。合併症を起こすかもしれません。手術がうまくいっても、1カ月後に再発するかもしれません。キャンサーボードでは、過去のエビデンスやデータから、「手術をしてもあまり意味がないのではないか?」というディスカッションになる可能性があります。でも、外科治療のよいところ、外科医のやりがいは、「難しくても、完全切除できれば、再発しない可能性がある」ことですよね。「えっ、あの患者さんが5年も生きられたのか!」ということが実際にあるのです。私はそんな患者さんからいただいた手紙も大事にとっています。
ですから私は、いかに難しくても完全切除できる可能性があり、患者さんが希望するならば、手術に挑戦したい。困難な手術に立ち向かうのは、恐いです。でも、その恐怖に負けてしまったら進歩はありません。私だったら、「この先生に」と命を懸けて任せたら、「危険だからできません」と言われてがっかりするよりも、手術を受けて死ぬ方が悔いはありません。患者さんが自分だったら、親や子供だったらどういう選択をするか考え、説明します。それで納得してくれた患者さんは、悪い結果になっても納得していただけると信じています。患者さんが望む手術であれば、最大の努力で応える。個別化の時代だからこそ、若い先生方には、そういう気持ちをもってほしい。(了)
インタビュー実施日・場所/2021年5月11日・つくば国際会議場
- 岡⽥ 守⼈(おかだ もりひと)
広島大学原爆放射線医科学研究所腫瘍外科教授、広島大学大学院医系科学研究科腫瘍外科教授、広島大学病院副病院長/呼吸器外科教授 -
1988年、奈良県立医科大学卒業。’88年、神戸大学医学部第2外科入局。’91年、神戸大学大学院医学系研究科(循環呼吸器外科)入学。’95年、同修了。’99年、米国ニューヨーク・コロンビア大学(胸部心臓外科)faculty。2002年、兵庫県立がんセンター呼吸器外科医長。’04年、同呼吸器外科長。’07年、広島大学腫瘍外科教授。専門は肺がんの胸腔鏡手術、根治的縮小手術(区域切除)、ロボット手術等。同年、環境省 中央環境審議会専門委員。’08年、第一回日本呼吸器外科学会学会賞。’20年、AATS Master Surgeon(右画像参照)。2020年には「区域切除」に関して、世界最高の胸部外科学会であるAATSで伝説的外科医Master Surgeonとして招聘講演を行った。画像はAATSのWebサイトより引用(公式ツイッター*で閲覧可能)。
*https://twitter.com/AATSHQ(2021年10月12日閲覧)
- 参考文献
-
- Video Assisted Thoracic Surgery
- ハイブリッドVATSは胸腔鏡の低侵襲性と、従来の直接見たり触ったりする手術の確実性を両立した手術。岡田守人先生が命名(Okada M, et al:Chest, 128:2696-701, 2005)
- Ng CSH, et al:Thorax, 68:681, 2013/Dziedzic D, et al:Minim Invasive Surg, 2015:Article ID 938430, 2015
- AATS(American Association for Thoracic Surgery)心臓血管外科・呼吸器外科領域の世界最高峰の学会